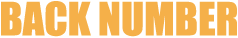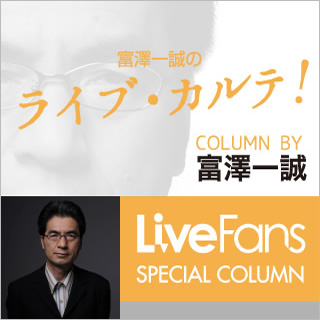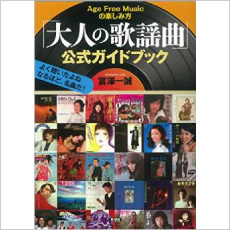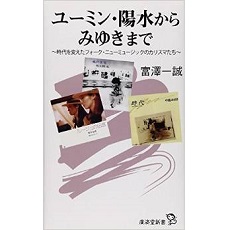第44回
岡林信康と吉田拓郎は特別な存在!
2017/01/25
〈山下洋輔×岡林信康ジョイント・コンサート〉(2016年12月28日、東京EX THEATER ROPPONGI)
2人がなぜ特別なのか?それは単なる歌を超えた存在だからだ。
「“反体制の英雄”岡林信康」
かつて“怒れる若者の季節”と呼ばれる時代があった、60年代後半から70年代にかけて、ベトナム反戦、学園紛争、安保反対と嵐が吹き荒れた時代である。
若者たちの“フォークの神様”岡林信康。そして彼の歌、「友よ」が生まれたのは、この“季節”の中からであった。若き闘士たちは、昨日まで歌っていた「インターナショナル」を捨て、デモや集会で「友よ」を大合唱した。闘いに疲れ切った若者たちは、夕闇の中で憑かれたようにこの歌を口ずさんだ。「夜明けは近い」と。
この歌で岡林は〈反体制の英雄〉に祭り上げられることになる。新聞は岡林を芸能欄ではなく社会面で取り上げた。それに伴って、岡林を中心メンバーとする関西フォークは演歌・歌謡曲にはない思想性に付加価値を持つようになる。つまり、岡林はフォークを“ただの歌”から解放したというわけだ。
“反体制”のという形容詞がつくぶん、そこには知的な薫りが漂っていた。岡林がフォークを“ただの歌”から解放したとすれば、次に登場する吉田拓郎はそれを受けて、フォークを若者全体にさらに浸透させた役割と言えるだろう。その結果、拓郎は“若者の英雄”となったのだ。
“反体制の英雄”と“若者の英雄”――この違いは、70年の“前”と“後”という〈時代〉の背景を抜きにしては語れない。
60年代半ば頃から、世界でベトナム戦争反対の無数の市民運動が高まり、日本の若者たちも例外ではなく小さな居住地、教会、職場、学校などで集会が開かれた。そこへ若者たちは参加した。そして“フォーク”という手段で戦争反対を訴えるようになった。こうしてベトナム戦争をひとつの契機として関西フォークの歴史は始まるのである。
高石ともやは自分の詞(つまり言葉)で自分の歌を歌った。それが人々に新鮮な驚きを与えた。高石に触発され、岡林信康、中川五郎らが歌い出し、彼らはそれぞれ時代や社会の状況を把握し「今言わなければならないこと」を自分の詞で自分の曲で歌い始めた。
それは主に社会に対する痛烈なプロテストだったが、時代が時代(ベトナム戦争から70年安保)だけに、彼らの歌は強く支持された。特に68年から69年かけては“プロテスト・ソング”が全盛だった。すなわち「戦争をやめろ」である。
これが昂じたのが新宿西口におけるフォーク・ゲリラだった。彼らはギターを持って西口広場に集まり戦争反対を訴えた。
しかし、「新宿西口広場での演説、合唱、その他の人寄せ行為、ビラのはりつけ及び配布、署名による寄付行為、許可のない物品の売買その他」は道交法、鉄道営業法によって禁止され、機動隊によってけ散らされた。69年7月19日のこと。7月26日午後3時頃、機動隊ができかけた歌の輪をけ散らした後に再び歌の輪が作られることはなかった。
そして70年、安保自動延長。それに伴い、挫折感がたくさんの若者たちの心を包んでいった。こうした運動と無関係でなかったフォークも大きなショックを受けた。
岡林は「今まで外にかみついてばかりいたけど、実は自分の中にこそ、かみつかなければならないところがあるのではないか」と、それまでの自分を総括した。
これはどういうことかというと、70年安保を境にして“外”に向いていた眼(意識)が“内”に向かい始めたこと、つまり、社会に対して痛烈にプロテストしていたものが自分自身に向けられ、自分の生活に根ざした歌が生まれたということだ。すなわち“生活派フォーク”の誕生である。プロテスト・ソングをベースにした関西のフォーク・ソング運動はここで終わった。
しかし、次の新しい波は既に用意されていた。岡林、高石が精力的に地方を回って“フォークの種”を植えつけたことにより、その中から新しいフォーク・シンガーたちが生まれてきたのだ。
その代表選手が《吉田拓郎》である。
拓郎のフォークの特徴は、70年前の岡林のフォークが「今俺たちが歌わねばならない」的使命感があったのに対し、「俺は歌いたいから歌うんだ」という、もっと自由な発想のものだった。
戦争なんて関係ない。政治社会問題なんて関係ない。俺にとってもっと切実なのは自分の生活と人生をどうするかということだ。そんな個人の自己主張、これが大きな特徴だった。
岡林と拓郎のフォークの違い――それを一言で表現するならば“私たちの歌”から“私の歌”への移行である。
岡林の「私たちの望むものは」という歌がある。この歌を初めて聴いたとき度肝を抜かれたものだ。“社会”とか“殺す”とか“奪いとる”とか、それまでの歌謡曲には絶対に出て来ない言葉がひんぱんに使われていたからだ。こんな歌があってもいいものか?
そのとき、私の考えていた歌の概念がガラガラと音をたてて崩壊していくのを感じた。なぜだかわからないが、戦慄を覚えた。これはすごい。自分の言いたいことを言い切ってっている。そう思うと“連帯感”が生まれ、自然に体がブルブルと震え出した。武者震いである。
「“若者の英雄”吉田拓郎」
それからしばらく経って拓郎の歌を聴いた。自分のことを歌っていると感じたものだ。
70年4月、私は東大に入学したが、すぐに中退してしまった。大学に入学した時点で、東大に対する憧れ、魅力がなくなってしまったからだ。それからは何の目的もない空しい日々が続く。しかし、こんなはずじゃなかった、という思いと焦燥感は常に持っていた。
そんな大学1年の終わり頃、ラジオの深夜放送で実にショッキングな歌を耳にした。拓郎の「今日までそして明日から」だった。
初めはなに気なく耳に入ってきた歌だったが、いつしか「そうだ。その通りだ」とうなずいている自分を発見してびっくりしたものだ。私の今の心情を見事に歌い切っていた。そこに“共感”を覚えたのだ。
こんな歌があったのか。そう思うと、いてもたってもいられなかった。私と違って拓郎はフォークを歌うという行為によって、何かをつかもうとしているようだった。少なくとも私にはそう思えた。そのとき、拓郎こそ、私にとって人生の指針ではないかと思った。
拓郎との出会いで、私は拓郎のように行動を起こさなければならないと決心した。私の“青春の風”が拓郎と共鳴して反応を起こし騒いだのだ。
それからすぐに大学を中退した。20歳のことだった。つまり、私は拓郎に刺激を受け、触発され、跳んだというわけだ。その意味では、拓郎の歌によって、私の生き方は確実に変わってしまったと言っていい。いや、私だけではないだろう。たくさんの若者たちが私と似た体験をしたはずである。そこが拓郎の歌にある“共感”の凄さなのだ。
40数年程前のあの“衝撃”と“共感”を再び共有したい、と私は思っている。いや、私だけではない。あの頃、岡林と拓郎の歌に触発された者にとっては、そのときの熱いマグマが未だ燃えたぎっているのだ。そのマグマを爆発させる誘導剤ともいうべきライブこそが、私にとってはまさに〈ベスト・ライブ〉なのである。
あなたの心のマグマは燃えたぎっていますか?
(文/富澤一誠)
【関連リンク】